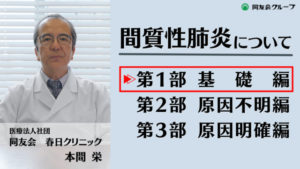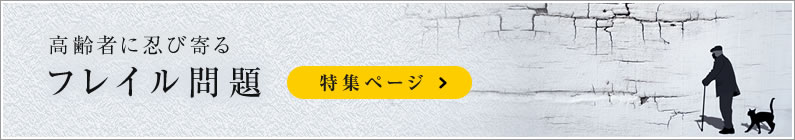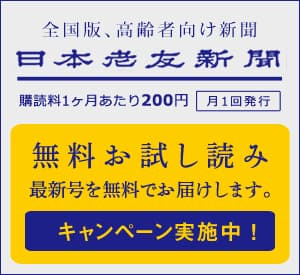ニュース
「手作り味噌体験教室」が人気!老舗「小泉麹屋」(横浜市)が開催

今日私たちは、あらゆるものが進化した中で暮らしている。新しい物や技術が現れて市場に出回ってきても、最初はためらっていたのに、しばらくするとその状況に慣れきる。その一方で、あえて「昔ながら」にこだわる人、挑戦する人もいる。そんな「昔ながら」の体験のひとつに、味噌作りがある。実は以前から人気の体験教室のようだ。「心にも体にも良い」味噌作りをご紹介しよう。
麹は食材の旨味引き出す
日本人の健康支えるお味噌汁
神奈川県横浜市に、創業明治元年とういう老舗の小泉麹屋がある。麹を販売するのはもちろん、農家が持ち込んだ米や麦を麹にして返すちんこうじ「賃麹」というものをしてきた。
時の流れとともにやがて味噌を作り、販売するようになる。そして現代表である五代目麹屋・小泉聡さんは、今、手作り味噌体験教室を広く開催している。その実績は20年にもなるという。
小泉さんは言う。
「日本人は、古来より自然の恵みをおいしくいただく食文化を育んできました。食材がもつ美味しさをそのまま食する、それが和食の知恵です。麹は食材の旨味を引き出すスターター。食材を発酵させて栄養を豊かに、そして美味しくしてくれます。私は、一日一杯のお味噌汁は日本人の健康を支えている、と思っています」
その思いが、手作り味噌体験教室の人気と継続につながっているのだろう。
「手前味噌」を伝承する
五代目・小泉聡さんの思い
では、味噌作りとはどんなものか、小泉麹屋の教室を通して紹介しよう。
「手作り味噌体験教室の始まりは、まず、道具と素材の確認から。麹、煮上がったばかりの大豆、塩、樽が基本です」
と、実際に指導にもあたる小泉さん。
「次にいよいよ作業です。大豆を潰していくのですが、どの程度潰すかは好みで。少し豆が残るように粗く潰してもいいですね。次に潰した大豆と麹、塩の入った樽に入れ、よく混ぜ合わせます。よく混ざったのを確認して、お団子にします」
この豆をつぶす感触が楽しく、癒やされるという人も多いという。
「そのお団子を樽の底に隙間がなくなるように投げ込み、底がみえなくなったら上からギュッと押し付けます。こうすることで空気が抜けて、かびの発生を防ぐのです」
団子を投げつけたときの音や行為にも、心地よさを感じる人がいるそうだ。

体験教室の所要時間は約1時間半。その合間に聞く麹の話も興味深い。
「大豆を麹菌で発酵させたものが味噌です。体験教室で使う麹は、米麹のほかに大麦麹、小麦麹、もち麦麹。米味噌は米麹、麦味噌は麦麹を使ったもの、ということですね」
また腐敗と発酵の違いも教わった。
「発酵は、人の体によい菌が働くこと。例えばチーズや納豆、紅茶がそうですね。一方、腐敗は人に悪い影響をもたらす菌が働いたということです」
手前味噌という言葉があるが、これはかつて各家庭で味噌が作られるのが普通だった頃、各自が自分の味噌を自慢し合ったことから生まれた言葉だ。自分が作った味噌にはそれだけ思い入れがあり、また美味しかったのだ。
「手前味噌」を伝承するお手伝いをしたい、小泉さんのそんな思いのこもった手作り味噌体験教室、ご興味のある方は次にお問い合わせを。小泉麹屋での体験教室のスケジュールは、月に10回以上組まれていることも。また、作る味噌の種類も豊富で興味をそそられる。手作り味噌出張講習会、オンライン味噌作り体験教室など、参加者が習いやすい環境を準備している。
【問い合わせ先】
合資会社 小泉麹屋
神奈川県横浜市港北区菊名5―24―25
TEL:045・432・7488
https://www.koujiya.com/
この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。
- 今注目の記事!