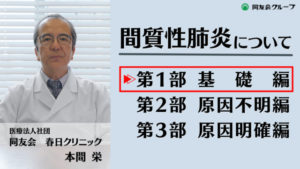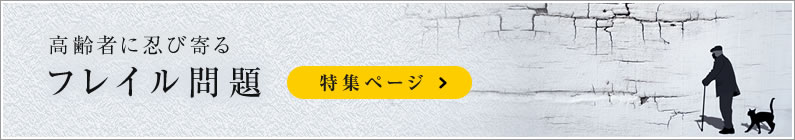コラム

マコのよもやま話 | 和泉 雅子
連載27 はまっちゃったあ

おフランスから帰国したその足で、フー先生(石井ふく子先生)をたずねた。フー先生は、日本舞踊の名手である。さっそく、お師匠さんを紹介していただいた。「私の友人で、教え上手の先生がいるの。そこがいいわ」麻布二の橋の、花柳梅静(はなやなぎうめしず)先生を訪ねた。
一人で着物を着たことがないが、どうにか着て、所作台へ。扇を置き、おじぎ。扇を両手で持ち立ち上がろうとしたが、さっぱり立てない。日本舞踊の奥深さを知った。一念発起。3年半、一日も休まずお稽古に通った。
日本舞踊は、長唄で踊ることが多いと気づき、梅静先生に紹介していただき、長唄を習うことにした。日吉小暎(ひよしこえい)先生だ。日本橋三越前の道をちょいと入った、お寿司屋さんの二階がお稽古場。週2回のお稽古を、休まず熱心に通った。三味線は才能なしだったが、楽しくて夢中になった。家族はあきれた。朝だろうが、真夜中だろうが、私の音痴な歌と、下手っぴーな三味線が聞こえてくるのだから。「粋だねえ」なんてもんじゃない。大迷惑だったに、ちがいない。
三味線に夢中になった私、フー先生のお母さんが、小唄・三升(みます)流の家元だったので、押しかけ弟子で、小唄のお稽古にも励んだ。
日本舞踊、長唄、小唄のお稽古をしていて、フッと、気づいた。「間」が大事なんだ、と。そこで、小暎先生に紹介していただき、鼓(つづみ)を習うことにした。藤舎成敏(とおしゃなりとし)先生(現・藤舎流家元・呂船(ろせん)先生)だ。先生を始めたばかりだったので、偶然私が第一号の弟子となった。奥さまの伊勢弥生(いせやよい)先生は、芸大のお三味線の先生。伊勢先生のお三味線で鼓のお稽古とは。なんとも贅沢でーす。
成敏先生「まさこちゃん、毎日お稽古にいらっしゃいネ」言われた通り、仕事の空き時間を見つけると、素っ飛んでってお稽古をつけてもらった。日活のテレビ映画とスタジオドラマと歌と司会、それにお稽古。天手古舞いの毎日。でも「これが私流」と、毎日ご満悦だった。
休まないでお稽古したのが良かったのか、それぞれ、お名前をいただくこととなった。ただ、日本舞踊だけが名取り試験があると言う。課題は『娘道成寺』。そこで、久里子姉ちゃん(波乃久里子さん)が同じ事務所だったので、中村富十郎さんを紹介していただき、ご指導していただくこととなった。富十郎さんは、歌舞伎役者さんの中で、踊りがあざやかで、声良し、演技良し、大ファンの役者さんだ。
富十郎さん「まず、踊ってみて」。私、どんどん踊るうちに、富十郎さん、だんだんむずかしい顔に。「手足だけで踊らないのよ。膝を折るには、腰のグリグリをグッと地に下げるの。ホラ、膝が折れたでしょ。踊りは、背骨と貝殻骨で踊るんですよ。指をさす時も、手でささないで、貝殻骨からさすんですよ。ホラ、指さしがきれいでしょう」。なんと、ありがたいご指導。全身がブルブルっとふるえて、マンガでよく見る。瞳にメラメラと炎がもえあがった。おかげさまで、花柳流の名取り試験、合格。ヤッター!
さて、いよいよお名前。日本舞踊は「花柳静雅子(しづまさじ)」。小唄は「三升八重雅(やえか)」。名付け親は、もちろん、フー先生です。長唄は「日吉児円(こえん)」。名付け親は、日本テレビの『ほんものは誰だ』で長年レギュラー回答者で共演していた、作家の柴田錬三郎先生。先生は小説の中で「おえん」という名の女性をたびたび登場させる。それにちなんで児円となったが「なんで一円二円の円なの」と私ブリブリ。鼓は「藤舎雅子(まさこ)」。名付け親は、京都先斗町(ぽんとちょう)の藤舎流の大先輩が、雅子を譲って下さった。先々代の家元が、江戸時代に造られた鼓を譲って下さり「名披露目は、この鼓で『勧進帳』を打ちなさい」。東京の国立小劇場と京都先斗町の劇場で『勧進帳』を打たせていただき、思い出深い名披露目となった。
こんなに邦楽にのめり込んだのも、あの、おフランスの、あのおパリの、赤っ恥のおかげ。あああ、はまっちゃったあ。じゃあ、またね。
この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。
- 和泉 雅子
- 女優 冒険家
- 1947年7月東京銀座に生まれる。10歳で劇団若草に入団。1961年、14歳で日活に入社。多くの映画に出演。1963年、浦山監督『非行少女』で15歳の不良少女を力演し、演技力を認められた。この映画は同年第3回モスクワ映画祭金賞を受賞し、審査委員のジャン・ギャバンに絶賛された。以後青春スターとして活躍した。
1970年代から活動の場をテレビと舞台に移し、多くのドラマに出演している。
1983年テレビドキュメンタリーの取材で南極に行き、1984年からは毎年2回以上北極の旅を続けている。1985年、5名の隊員と共に北極点を目指したが、北緯88度40分で断念。1989年再度北極点を目指し成功した。
余技として、絵画、写真、彫刻、刺繍、鼓(つづみ)、日本舞踊など多彩な趣味を持つ。 - 主な著書:『私だけの北極点』1985年講談社、『笑ってよ北極点』1989年文藝春秋、『ハロー・オーロラ!』1994年文藝春秋。
- 今注目の記事!